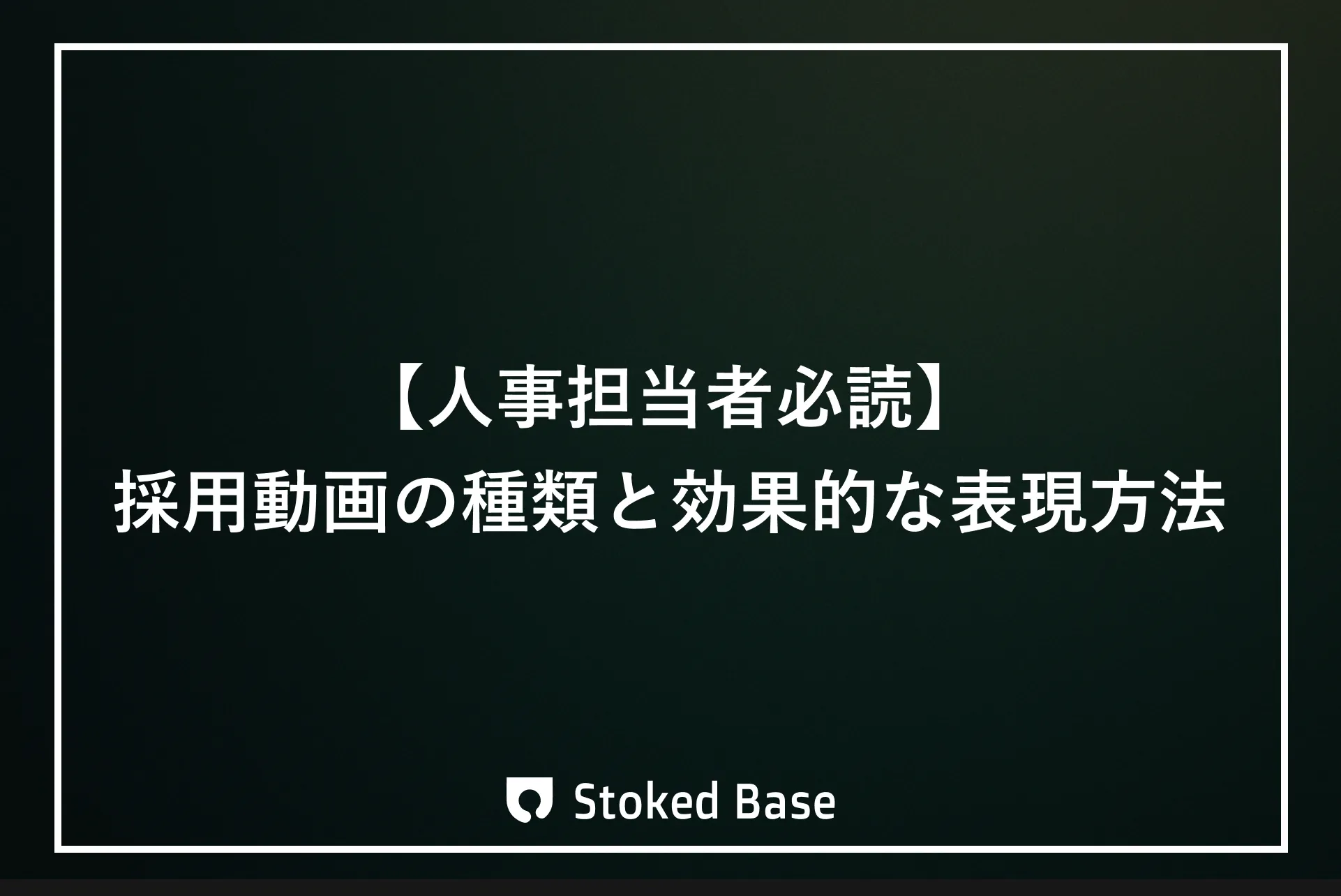
目次
まずは「何を変えたいのか」をはっきりさせるところから始めます。採用動画は、求職者の集客から応募後の理解促進、内定承諾率の向上まで、採用プロセス全体に効きます。目的が明確になると、動画の長さや表現方法、公開先の判断がブレません。
求人との最初の接点では、「何の会社か」「どんな強みか」を数秒で記憶に残る形で伝える必要があります。会社紹介の要点を30〜60秒に圧縮し、目を引く映像と印象的なキャッチコピーを組み合わせると、クリック率と会社名での検索が伸びやすくなります。各SNSプラットフォームごとに縦型・短尺のバリエーションを用意できると、求職者との接触回数が安定します。
仕事内容や評価の仕組み、チームの雰囲気が伝わると、会社とのミスマッチによる応募が減り、選考がスムーズになります。職種紹介や社員インタビューで日常の様子を具体的に見せ、業界の専門用語は字幕や図解でわかりやすく説明すると離脱を防げます。入社後のリアルな働き方を想像できる状態づくりが狙いです。
内定後の辞退理由は「働くイメージが湧かない」「配属・評価への不安」が多くを占めます。入社初日からの流れやサポート体制、評価の仕組みを動画で見える化すると、候補者本人だけでなく家族・周囲への説明もしやすくなり、承諾率が上がります。
色やロゴだけでなく、話し方・テンポ・音の”人格”を統一すると”その会社らしさ”が定着します。コーポレートサイトや商品紹介動画と雰囲気を合わせ、接点ごとに同じ世界観で重ねることが長期的な求職者獲得に効きます。
同じ「会社紹介」でも、狙う効果や見せたい”らしさ”によって最適な形式は変わります。主要な動画形式の特徴を理解し、課題に合わせて使い分けましょう。複数本を戦略的に組み合わせると、候補者の関心段階にフィットさせやすくなります。
企業の全体像を短時間で伝える核となる一本です。会社の歴史や事業を羅列せず、強みと「社会への貢献」に絞ると記憶に残ります。採用の文脈では”働く意味”へつながるナレーション設計が有効です。
何を作り、誰がどの価値を得ているかを詳しく示します。利用シーンや成果指標まで映像で見せると、候補者は自分のスキルがどう活かせるかを理解できます。技術・専門職の採用で特に効果的です。
価値観や成長のリアルが伝わる定番です。質問は「入社前の不安」「成長実感」「評価の仕組み」など応募者の疑問に直結させます。年代や職種を並列に配置すると、幅広い共感を得られます。
一日の流れや意思決定の現場を追うことで、文化や人間関係が自然に伝わります。過度な演出を避け、”会話の温度””判断の基準”をそのまま収めるほど信頼につながります。
働く環境・設備・周辺環境は生活イメージを左右します。固定された映像だけでなく歩きながらの撮影で見せるとサイズ感や快適さが伝わり、通勤や働き方の具体的なイメージが湧きます。
経営陣の”意思表示”を短尺で明確に伝える動画です。理念や事業の向かう先を候補者視点の言葉に置き換えて語ると、共感と納得が同時に得られます。
よくある疑問に動画で答えると、文章より理解が進みます。配属や評価、残業・リモートワークなどは、制度と日常運用の”具体例”を併記すると説得力が増します。
「らしさ」は偶然ではなく設計で再現します。先に言葉(メッセージ)と視覚(雰囲気とルール)を固め、シーン・音・文字表現まで一貫させると、制作のブレと修正作業が大きく減ります。
誰に何を変えてもらいたいかを具体化します。新卒・中途・職種別で動機や情報への感度は違うため、同じ素材でも強調点を変える設計が必要です。
「結局、この会社は何がすごいのか」を一言に集約します。タイトルやナレーション冒頭、サムネイルの文字でも同じ言葉を繰り返し露出すると、記憶に残ります。
ブランドの人格を決める要素です。配色やフォント、撮影の光、編集テンポやBGMの質感を規定し、どの動画でも”同じ会社感”を出します。過剰な装飾より、余白で品位を保つのがコツです。
ロゴの出し方、アニメーション速度、カラー占有率を統一します。動画の最初・最後の秒数や動きの”微妙な違い”が世界観を壊すため、あらかじめルール化しておきます。
視聴継続の山場を先に設計し、要点は”前倒し”で提示します。主メッセージは章ごとに短く反復し、最後にもう一度要約すると、視聴後の記憶が高まります。
同じ内容でも、映像スタイルや編集テンポ、音・字幕の選び方で響き方は大きく変わります。候補者の”見たい時間”と”知りたい深さ”に合わせて、動画の長さ・情報密度・テンポを調整しましょう。縦型やモバイル字幕など視聴環境を前提に置くことが肝心です。
視覚的インパクトを強くしたい時はモーショングラフィックス、文化の空気を伝えたい時はドキュメント寄りが有効です。採用課題と視聴デバイスを見て使い分けます。
候補者が知りたい項目を質問ガイド化し、過剰な台本感を減らすと”人間味”が残ります。声の質感や語りの速度も印象を左右するため、読み手の選定とリハーサルに時間を割くと安定します。
字幕は”要点の抽出”に徹します。1カット1メッセージを原則に、読みやすいサイズとコントラストはスマホ基準で設計します。画面下三分の一に情報を集中させすぎないバランスも重要です。
スムーズに進める鍵は「意思決定の順番」を決めることです。目的 → KPI → メッセージ → 構成 → 見せ方 → 撮影 → 編集 → 配信 → 検証の順で合意を作れば、手戻りが最小化します。以下は代表的な流れです。
採用課題、ターゲット、視聴環境、想定の長さ、公開チャネル、スケジュール、予算の前提を文章で固めます。ここで”やらないこと”も明記すると後工程が安定します。
コアメッセージを軸に、章立てと見どころ、撮影リスト、インタビュー質問票を作成。参考映像とNG例を並べ、雰囲気をすり合わせます。
事前の下見で光と動線を確認し、当日の人の稼働と動作を段取り化。同じシーンの複数アングル確保、部屋の音環境の事前チェックで編集の選択肢を確保します。
粗編で物語の骨格とテンポを決め、合意後に色・音・字幕を整えます。初稿の段階で”仕上がりの方向”が見えるよう、仮の色調整と仮BGMを当てると意思決定が早まります。
本編の承認後、短尺・縦型・サムネイルなど素材を一式化。公開先ごとの仕様(解像度・データサイズ・キャプション)に合わせて納品します。
良い動画でも、届かなければ意味がありません。自社サイト、求人媒体、SNS、説明会、スカウトメールなど、候補者の行動導線に沿って配置します。一本を分解して複数導線で”何度も記憶に残る”発想が効率的です。
ファーストビューや社員紹介の近くに配置し、視聴後の行動導線(エントリー・説明会予約)を明確にします。再生数より応募CVの改善を指標に置き、周辺テキストで補足を足します。
媒体ごとに興味を引く言葉の変更とサムネイル差し替えを行い、クリック率の底上げを狙います。文言のABテストは短いサイクルで回すのがポイントです。
来場できなかった層にも同等の情報体験を届け、取りこぼしを防ぎます。登壇前後で短尺版を提示すると記憶に残りやすくなります。
各プラットフォームのルールに合わせて、縦型・字幕必須で展開します。固定ポストやリール表紙でのファーストビュー作りが露出を押し上げます。
採用ページ訪問者への再アプローチや、高エンゲージ視聴者の類似配信で効率化します。動画内CTAは広告仕様に合わせて短く明快に再設計します。
YouTubeやサイト解析だけでなく、応募フォームのイベント計測まで接続します。視聴 → クリック → 応募の各段階でボトルネックを特定し、動画を直すのか導線を直すのかを切り分けます。
「全部盛り」「長尺化」「抽象先行」は典型的な落とし穴です。意思決定者が多いほど、最初に判断基準と”やらないこと”を共有しておくと迷いが減ります。権利やセキュリティなど運用上の要件も同時に整えましょう。
伝えたいことは絞り、絞った内容を軸に画・言葉・音を配置します。一本で全課題を解決しようとせず、目的別に分けると視聴体験がクリアになります。
企画段階で参考映像とNG例を並べて期待値を統一します。色や音、アニメーション速度などの”微妙な違い”が世界観を崩すため、参考動画等で方向を先にすり合わせします。
顔出し可否、第三者ロゴ、機密情報の映り込みを事前に整理します。音源は商用ライセンスの確保が必須です。公開前チェックリストを運用すると事故を防げます。
“作る”だけでなく”成果を広げる”視点を持つパートナーが理想です。実績の見栄えより、課題定義 → 表現 → 活用 → 検証までの一貫支援力と、コミュニケーション設計を見ましょう。
採用課題の把握と、動画以外の打ち手も含む提案ができるか。なぜこの表現なのかを言語化できることが重要です。
進行設計、撮影の安定感、編集の再現性、レビュー体制、バックアップ運用など、”トラブルを起こさない仕組み”を確認します。
納品データの権利範囲、二次利用、追加発生の条件を明確にします。分解用の元データの扱いは前もって合意しておくと後トラブルを防げます。
現状の課題から逆算します。何が伝わっていないのかを言語化し、そのギャップを埋める最短の動画形式を選びます。たとえば認知不足なら短尺のコーポレート、理解不足なら職種紹介やインタビューが有効です。
採用トップのファーストビューは30〜60秒、会社紹介は1〜3分が目安です。説明会やサイトの役割、視聴環境によって適正は変わるため、目的から決めるのが正解です。
内容・長さ・撮影規模で上下します。ストークベースの実績レンジは概ね30〜100万円が多く、分解して短尺複数本を同時に作る設計だと費用対効果が上がりやすいです。効果は再生数だけでなく、応募率・面談出席率・承諾率まで見て判断します。
採用動画は”設計 → 表現 → 制作 → 活用 → 計測”の連続です。まずは課題と伝えたい一言を紙1枚に整理し、対象とメッセージを絞り込むところから始めましょう。
StokedBaseは映像・YouTube・Web制作など複数のクリエイティブを横断し、採用課題から逆算した最適な動画と活用設計をご提案します。企画段階のアイデア出しだけでも、まずは気軽にご相談ください。