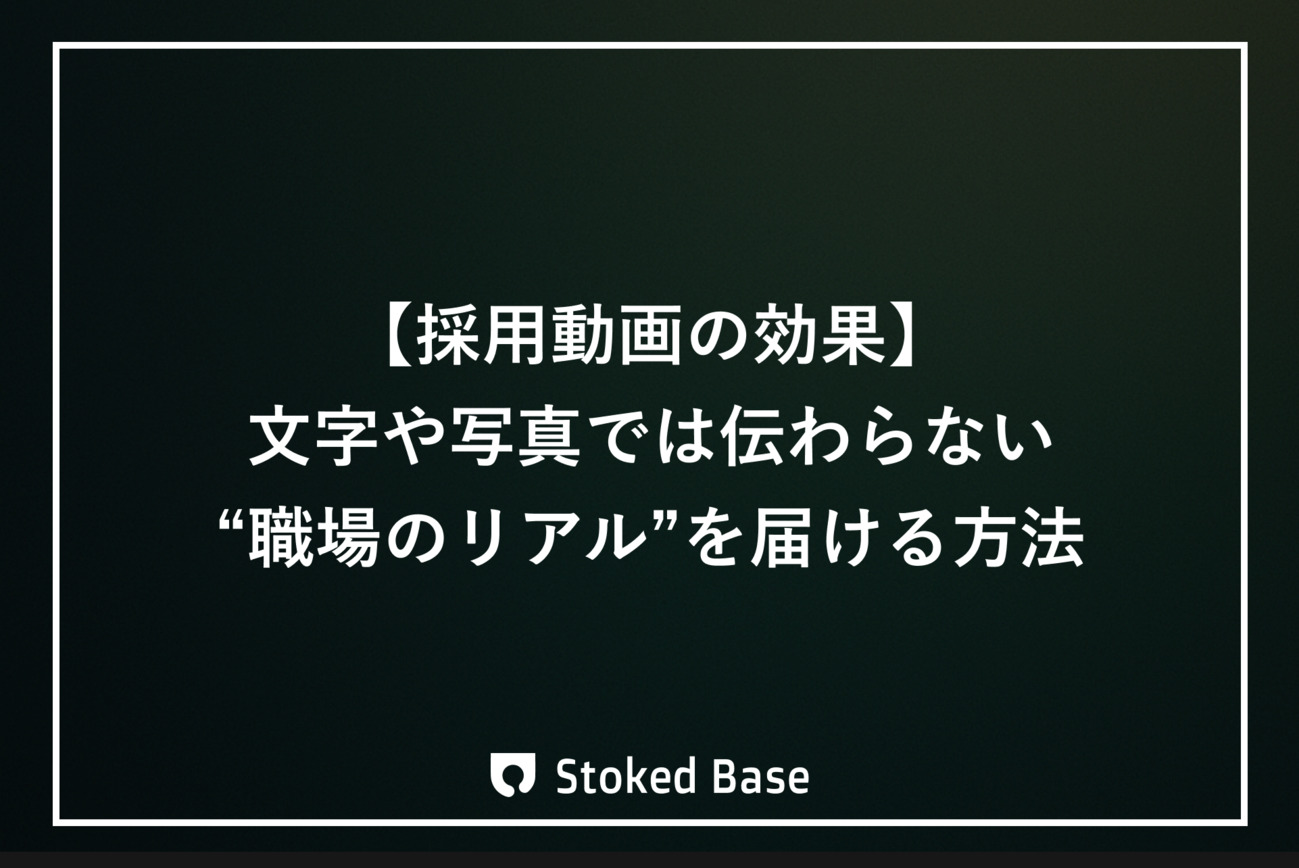
目次
文字・写真・説明会だけでは届きにくい情報があります。動画の強みは、仕事内容の動きや声のトーン、チームの距離感といった”非言語情報”をまとめて伝えられること。まずは採用活動でよくある「伝えたいことが伝わらない問題」を整理します。
文字は、給与や休日などの制度を正しく伝えるのに向いていますが、働くテンポや人柄の温度感といった肌感覚は伝わりにくいままです。写真は印象を補強できますが、切り取られた一瞬でしかなく、業務の流れや安全配慮の積み重ね、現場の賑わいと静けさの切り替わりまでは表現しきれません。候補者が本当に知りたい「どんな人が、どんな距離感で、どんなテンポで働くのか」は、時間の流れがある情報でこそ理解が進みます。
動画は表情の変化や声の抑揚、会話の間合いを通じて人柄を立体的に伝えます。作業音や現場音は、文字だけでは伝わらないリアリティを与え、安心感や信頼にもつながります。また、同じ内容でも”誰が語るか”によって説得力が変わるため、実際に働いている社員や管理者が自分の言葉で話すことが、候補者との心理的な距離を縮めます。
効果は「母集団の質」「歩留まり」「ミスマッチ低減」に分けて評価すると、社内での説明や運用判断がしやすくなります。ここでは、それぞれの観点で何が起きるのかを、実務に落とし込める言葉で解説します。
現場の実態や求める人物像を動画で明確にするほど、候補者は自分に合うかどうかを判断しやすくなります。結果として、適性に合わない応募が自然と減り、応募者数だけに頼らない”質の高い母集団”に寄っていきます。これは選考段階でのやり取りにかかる負担を減らし、面接の内容を濃くする効果も生みます。
文字や写真では伝えにくい”働くイメージの具体化”が進むと、候補者は一歩踏み出しやすくなります。仕事内容の流れ、チームの雰囲気、成長の実感といった要素が具体的に想像できるため、求人媒体や採用サイトの「応募」「説明会予約」ボタンのクリックに直結します。動画は、迷っている候補者の背中を押す最後のひと押しとして機能します。
選考前に現場の声や空気感に触れていると、候補者は自分の期待値を現実に合わせて調整できます。その結果、選考途中の「思っていたのと違う」というギャップが起きにくくなり、辞退率の上昇を抑えられます。内定後においても、入社後の具体的な働き方が想像できる状態は、不安の軽減につながります。
入社前から1日の働き方や評価の考え方、チームでのコミュニケーションの取り方を理解していると、入社直後のギャップが減ります。会社の文化や価値観とのズレが小さくなり、定着に向けた最初の立ち上がりが安定します。動画は”選ぶ側”だけでなく”選ばれる側”としての説明責任を果たす手段でもあります。
「採用動画」はYouTubeに限定されるものではありません。説明会や求人媒体、採用サイト、社内研修、社内ポータルなど、見せる場所ごとに適した形があります。ここでは、よく使われるタイプと狙いどころを整理します。
組織の存在意義、事業内容、社会への提供価値を短時間で全体像として理解してもらう内容です。初めて会社を知る候補者にとっての入口となるため、難しい専門用語を避け、事業の”なぜやっているのか”と”どのようにやっているのか”が同時に掴める構成が向いています。採用サイトの上部や説明会の冒頭で効果を発揮します。
実際の業務の流れや判断のポイント、必要な姿勢を”時系列”で見せるタイプです。どの場面でどんな連携が生じるか、どのような安全配慮や品質基準があるかまで触れると、現実的な期待値の設定につながります。中途採用の候補者には具体性を、新卒には理解のスピードをもたらします。
同じテーマでも立場が違えば見える景色が変わります。若手は成長の実感、中堅はキャリアの展望や役割の広がり、管理職は評価・育成の考え方に触れることで、候補者は自分の未来を複数の角度から想像できます。編集では、台本通りではなく”人となり”が伝わる余白を残すと効果的です。
制度の紹介に終わらず、日常のコミュニケーションの取り方や意思決定のスピード、挑戦に対する姿勢といった”実際の振る舞い”を映像化します。オフィスや現場の動線、休憩スペース、装備やツールの使い方などの細かい部分が、安心感や憧れにつながります。
入社後に何が求められ、どのように支援され、評価されるかを明確にします。学習のステップやメンター制度、面談の頻度と目的などを具体的に語ると、入社後のギャップを減らし、立ち上がりを早める効果があります。内定者へのフォローの場面で特に機能します。
動画は”感じ取る情報”に強く、文字・写真は”検索性と比較性”に強いという前提で設計するのが近道です。候補者は複数の企業を比較するため、各メディアの得意領域を分担させると理解が速くなります。
人柄、現場のテンポ、チームの距離感、音や空気、判断の背景といった、時間の流れがあって感覚的に理解できる要素は動画が最適です。理念やカルチャーを”語り”と”現場の映像”で行き来しながら見せると、言葉と体験が結びつき、記憶に残りやすくなります。
募集要項や選考の流れ、勤務地や勤務時間、制度・手当、スキル要件、よくある質問などは、文字と表で整理した方が候補者は後から見返しやすくなります。動画のすぐ下に要点をテキストで置くことで、視聴後の比較検討に移りやすくなります。
採用動画の成否は、撮って終わりでは決まりません。どんな候補者に向けて、どんな場面で見てもらい、視聴後にどんな行動をしてほしいかまでをセットで設計することが重要です。
「母集団の質」「応募・予約率」「辞退率」「定着」に紐づく仮説を先に立て、動画ごとに役割を分解します。たとえば、会社紹介は”初めて接触したときの理解促進”、職種紹介は”応募前の不安解消”、インタビューは”選考中の熱量維持”、オンボーディング動画は”入社後の立ち上がり”というように、それぞれのKPIの担当領域を明確にしておくと、効果測定と改善がしやすくなります。
採用サイトの該当箇所に埋め込み、求人媒体からのリンクや説明会スライドへの組み込み、限定公開URLを使った候補者向けメール配信など、候補者が自然に触れる導線を複数用意します。視聴直後に次の行動へ移れるよう、動画の近くに「応募」「説明会予約」「募集要項」「関連記事」などの導線を並べると、離脱を抑えられます。
照明と音声の品質は視聴体験に直結します。声が聞き取りづらい、顔が暗いだけで離脱率が上がります。編集では、テンポを早くしすぎてカットを詰め込みすぎず、語りに合わせて現場の映像を丁寧に差し込むことで、説明と体験の行き来が生まれます。字幕は、音を出せない環境でも視聴できるため必須です。
撮影の許諾や映り込みの管理、社外秘情報の隠し処理、個人情報の取り扱い、制服・安全装備の着用状況のチェックなど、公開前の確認の流れを明確化します。アクセシビリティの観点では、字幕・音声への配慮・色覚への配慮を初期から前提にすると、後から手戻りが減ります。
ここでは、人事の現場でよく出る疑問に答えます。いずれも一般的な考え方であり、業界の特性や職種の特性に応じて調整してください。
配信の設計が適切で、候補者の導線が整っている場合は、公開直後から説明会予約率や問い合わせの変化に気づくことが多いです。一方で母集団の”質”や定着といった中長期の指標は、一定の採用サイクルを見て判断する必要があります。公開後はアクセス数・視聴完了数・クリック数などの初期指標を週ごとに確認し、サムネイルや見出し、設置位置の微調整を重ねると効果が早く安定します。
視聴回数だけで評価しないことがポイントです。視聴完了率(最後まで見た人の割合)や重要パートの到達率、視聴後のクリック率(応募・予約・募集要項への遷移)、選考ステップごとの辞退率の変化など、行動に近い指標を重ねて見ます。動画単体ではなく、ページ全体の滞在時間やスクロール、関連リンクへの移動も合わせて見ると、改善のヒントが見つかります。
“伝える目的”と”視聴シーン”で変わります。採用サイトの冒頭なら短く要点をまとめ、職種理解を深めるパートでは少し長くても問題ありません。重要なのは、最初の数十秒で「何がわかる動画か」を明示し、要点ごとに章立てして見返しやすくすることです。長さよりも”必要な情報が迷わず取れる構成”を優先します。
現場の映像とナレーション、手元や道具のクローズアップ、図解やテキストアニメーションで補う方法があります。出演のハードルを下げるには、顔出しあり/なしを選べる設計や、短時間のコメント参加など、段階的な関わり方を用意しておくと良いです。
前提知識と知りたい深さが異なるため、入口は分けた方が親切です。新卒向けには会社の全体像や成長の機会を、中途向けには配属先の役割や意思決定のスピード、期待値の具体性を厚めに。共通の”核”を保ちつつ、視聴者ごとに見出しと導線を最適化します。
採用動画は、文字や写真では伝えきれない”非言語情報”を補い、母集団の質向上、応募・予約率の押し上げ、辞退と早期離職の抑制に効きます。効果を最大化するには、目的とKPIの分解、配信導線の設計、字幕・音声・照明といった基本品質、そして公開後の継続的な改善が欠かせません。
StokedBaseは映像・YouTube・Webを横断して、企画の壁打ちから配信設計、運用改善まで一気通貫で支援しています。自社の状況に合わせた最適な進め方を一度整理したい方は、お気軽にご相談ください。